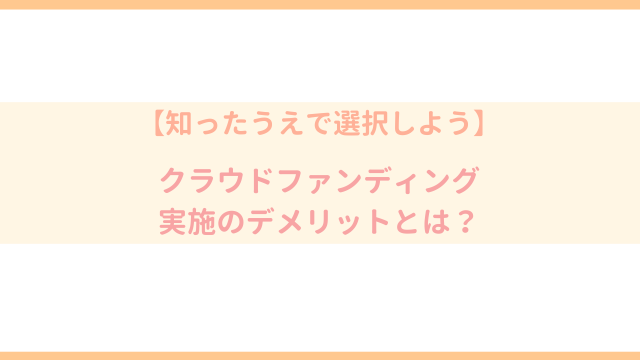
クラウドファンディングは、新商品やサービスを開発する企業にとって、とても有効的な資金調達手法です。
商品やサービスの認知向上を期待できる、ファン化が促進できる、テストマーケティングができるなど、実施することで様々なメリットがありますが、知っておきたいデメリットもあります。
こちらの記事では、クラウドファンディングのデメリットの他、クラウドファンディングを成功させるための戦略についても紹介していきます。
クラウドファンディングを活用するか否か、実施材料として参考にしてください^^
クラウドファンディングの種類によってデメリットが違う
クラウドファンディングには「購入型」「寄付型」「金融型」とさまざまな種類があります。
購入型クラウドファンディングとは、起案されたプロジェクトに対して、支援者がお金を支援しその対価としてサービスや体験、モノを受け取れる仕組みのこと。
寄付型クラウドファンディングは、御礼のお手紙や動画など対価性のないリターン品を設定できます。通常の寄付と同じイメージを持っていただければOKです!
金融型クラウドファンディングは、集めた資金を融資や事業などで運用し、得られる利益がリターンになります。
購入型クラウドファンディングのデメリット
目標金額を達成できる確約はない
設定した目標金額が達成できる確約はありませんので、クラウドファンディングで得られる資金だけに依存していると、プロジェクトを遂行できない可能性が高まります。
プロジェクトの中断はできない
クラウドファンディングの種類に限らず、立案したプロジェクトは原則として内容変更や中止ができません。
プロジェクトの内容を変更してしまうと、支援のタイミングによっては、不利益を被る支援者が発生する可能性があるためです。
プロジェクトの内容を変更することで、支援者の信用を損なう可能性も高確率になるため、どのようなプロジェクトで立案するかは慎重に考える必要があります。
プロジェクトを始める前には、どのようなコンセプトにするのか、なぜクラウドファンディングを実施したいのかをしっかりと考えたうえで望む必要があります。
支援金全額を事業に使用できない
補助金や助成金・公庫と違う点として、購入型クラウドファンディングを立案した場合、支援者の方にリターン品の返礼義務があるため、支援金額すべてが事業に投入できるわけではありません。
クラウドファンディングで集めたい資金がいくらなのかを考える際には、リターン品返礼にかかる送料や販管費、手数料などを加味したうえで、リターン品の価格設定を決定する必要があります。
アイデアを盗まれる危険性がある
クラウドファンディングは、プロジェクトの内容を誰もが閲覧できる状態になっています。競合企業などにアイデアを盗まれるリスクは避けられません。
クラウドファンディング後、特許取得を考えている商品やアイデアに関しては、プロジェクト終了後にページを非表示対応にすることは可能ですが、プラットフォームによっては要望が通らない可能性もあります。
SNSや広告を活用しないと成功が難しい
SNSの発信や広告を活用しない場合は、起案者の人脈や過去のおつながり、所属されているコミュニティによって支援金額が変わる可能性が高くなります。
SNSや広告の役割は、多くの方々にプロジェクトを「認知」してもらうきっかけを作ること。繋がりのない方からの支援を望む場合や、多くの方にプロジェクトを知ってもらいたいのであれば、広告やSNSの活用をおすすめします。
SNSや広告を使用できない場合や資金的に難しい方に覚えておいていただきたいのが、クラウドファンディング3分の1の法則です。
▽クラウドファンディング3分の1の法則とは?
https://yanomomo-writer.com/rule/
ガジェット系や物販系の商品ではない場合や、SNSや広告を活用しない場合は、支援のベースは基本的に身近な方や友人、知人になりますので、支援を依頼できそうな方々へのご連絡周りは必須となります。
手数料がかかる
資金が振り込まれる際、プラットフォームの運営会社に決済手数料を支払う義務があります。手数料はプラットフォームにより異なりますが、基本は調達した資金から10%~20%を引いた金額となります。
プラットフォーム会社に支払う手数料は、経費計上できます◎
寄付型クラウドファンディングのデメリット
リターン品がないため、支援が集まりにくい
購入型クラウドファンディングと違い、商品やサービスなどの経済的なリターン品がないため、支援が集まりにくいデメリットがあります。
支援したお金がどのように使われているのかを支援者は注目しているため、資金の使い道や活動報告の共有などを丁寧に行う必要があります。
デメリットを理解したうえで、挑戦するか検討しよう
購入型、寄付型クラウドファンディングともデメリットがあることを理解したうえで、プロジェクトに挑戦するか否かを検討していきましょう。
クラウドファンディングにデメリットはあるものの、多くのメリットがあるのも事実。ご自身の商品やサービスがクラウドファンディングに向いているかなど相性もあります。
個人的には、やってみたいと感じるのであればクラウドファンディングにぜひ挑戦してみていただきたいなと思います^^
あなたの商品やサービスを待っている方々は、必ずいますよ!
やもにクラウドファンディングの相談をしよう!
「事前準備に不安があるから伴走してほしい」
「クラウドファンディングについて詳しく知りたい!」等
クラウドファンディングや広報周りの相談・サポートを希望する方は、無料個別相談へのお申込みもしくはLINE公式アカウントよりお気軽にご相談くださいね^^
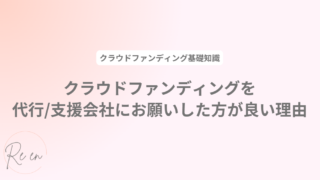

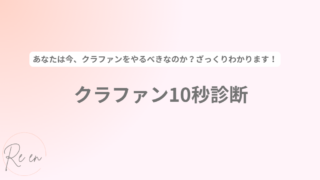

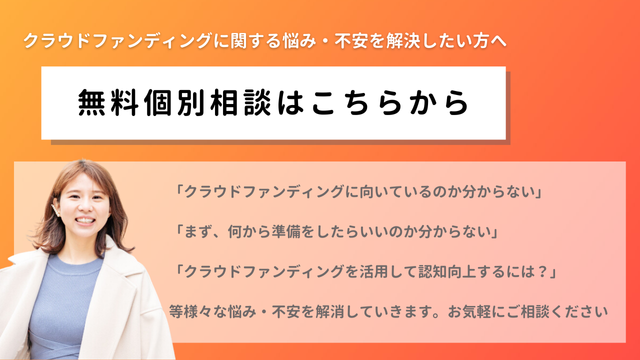

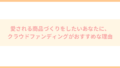
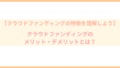
コメント